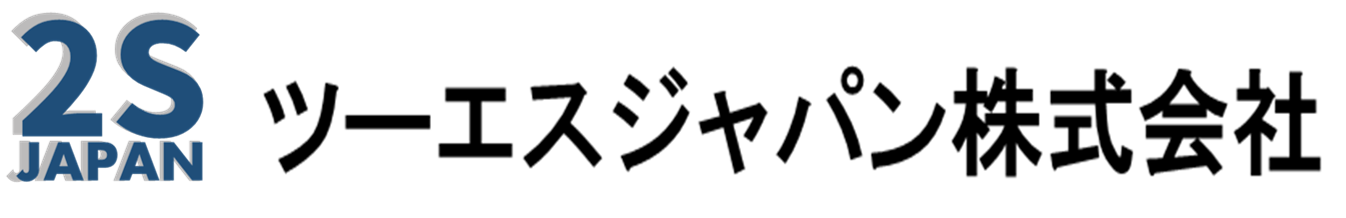まず最初に、はっきりさせておく必要があります。
世の中で使われている「光触媒」という言葉は、科学用語としても、技術用語としても、すでにかなり曖昧に崩れています。
一般には、「光を吸収して化学反応を促進し、その過程で自らは消費・変質しない物質」と定義されますが、この定義を文字通り厳密に満たす物質は、実際には存在しません。
触媒である以上、表面状態・電子状態・吸着状態は必ず変動します。
「変質しない」という表現は、現象の正確な記述ではなく、理論上の約束事にすぎません。
それでもなお、この定義に「最も近い性質」を持つ材料として扱われてきたのが酸化チタン(TiO₂)です。
“完全に変化しない物質”だからではなく、「変化が比較的小さく、長期的に触媒として振る舞える」という意味で選ばれてきただけです。
つまり、酸化チタンが特別なのは「変質しないから」ではなく、「変質しても、なお触媒として成立し続ける程度に安定だから」です。
ここを取り違えると、すでに光触媒の理解は歪み始めます。
■ 光とは何か― 光触媒に関係する「光の正体」 ―
光は電磁波であり、同時に光子(Photon)というエネルギー粒子でもあります。
光触媒において重要なのは「紫外線という名前」ではなく、光子が持つエネルギー量です。
にもかかわらず、「光触媒は紫外線で反応する技術」という説明が広まりました。
これは便利な言い方ではありますが、物理的には不正確です。
正しくはこうです。
光触媒は「十分なエネルギーを持つ光子を吸収したときに反応する技術」です。
酸化チタンの場合、その閾値は約3.2 eV前後です。たまたまそのエネルギー領域が紫外線帯に重なっているだけです。紫外線だから反応するのではありません。エネルギーが足りているから反応しているのです。
この差は、技術理解として決定的です。
■ 光を吸収して反応するとはどういうことか
物質が光を吸収すると、電子が励起されます。
この電子状態の変化を起点として反応が進行する現象を光誘起反応と呼びます。
この性質自体は、酸化チタンだけのものではありません。
酸化亜鉛 酸化タングステン 酸化鉄 酸化銀 酸化ケイ素
多くの酸化物が光に反応します。
ただし、それらの多くは反応過程で
変色する 還元される 溶解する 構造が崩れる
など不可逆変化を起こし、触媒として成立し続けません。
酸化チタンが選ばれた理由は、「反応するから」ではなく「壊れにくいから」です。
この一点だけです。
■ 光触媒反応の本質(本来知られていたこと)
実は、「酸化チタンに光が当たると、空気中の酸素が吸着され、原子状活性酸素を経由して酸化反応が進む」という現象は、100年以上前から知られていました。
光触媒の本質は、水を分解することではありません。空気中の酸素を活性化することです。
この時点ですでに、現在流通している説明の多くは、構造的にずれています。
■ 歴史整理と、決定的なすり替え
1972年に発表された本多–藤嶋効果は、
酸化チタン電極 白金対極 電解質溶液 外部回路を用いた、完全な光電気化学反応です。
これは触媒反応ではありません。電極反応です。にもかかわらず、この現象が
「光触媒が水を分解する」「光触媒は強力に何でも分解できる」
という比喩で語られ、やがてその比喩が“定義”として独り歩きしました。
ここで起きたのは発見ではありません。定義のすり替えです。
■ 添加型光触媒が生んだ構造矛盾
その後、市場では樹脂で固め、シリカで覆い、金属をドープし、吸着材を混ぜるという「強く見せる」ための設計が広がりました。
しかしこれは、空気と接する表面で成立するはずの反応面を自ら潰している構造です。
反応が弱くなるのは当然です。設計そのものが、光触媒の原理と矛盾しています。
■ まとめ
光触媒とは「変化しない物質」ではない
酸化チタンは「壊れにくいから使われただけ」
紫外線は本質ではなく、光子エネルギーが本質
本多–藤嶋効果は光触媒ではない
比喩が定義に化けた瞬間、すべてが歪んだ
添加設計は原理と逆方向に進んだ
だからこそ、「従来型の光触媒が実環境で期待通りに機能しなかった」のではありません。
そもそも、理解の出発点が歪んでいたのです。
ここを正しく理解しない限り、どんな改良も、どんな規格も、同じ場所を回り続けるだけになります。