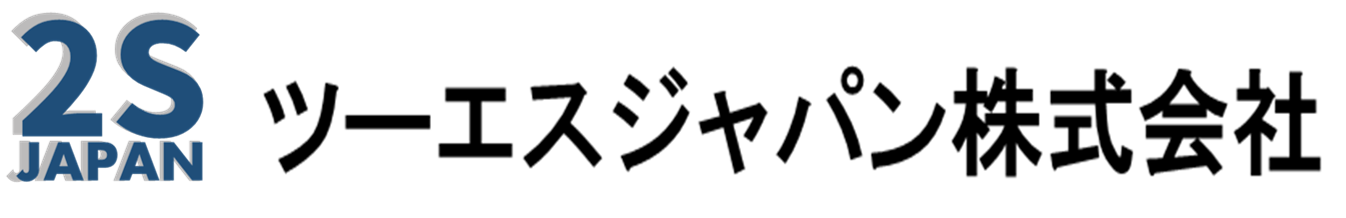光触媒に「常識」など存在しない。
存在しているのは、常識であるかのように固定化された説明体系だけである。

現在「光触媒の常識」と呼ばれているものは、自然に形成された科学的合意ではない。
研究拠点、研究テーマ、評価軸、説明の型が一か所に集中し、その構造の中で作られ、流通し、定着した物語にすぎない。
そして、その中心にあったのが東京大学である。
東京大学で行われていた研究は、本来、電極、水溶液、外部回路、電気化学系という
極めて限定された実験条件を前提としたものであった。
それは「空気中で使われる材料」の研究ではない。水中電気化学反応を扱う基礎研究である。
にもかかわらず、その反応モデルは、いつの間にか建材、空気中、乾燥環境、屋外使用という、まったく別の世界へ無条件で拡張された。これは発見の拡張ではない。理論の発展でもない。
適用範囲の誤転写である。
水中実験の反応系、空気中材料の説明、販売用の言葉。この三つが区別されないまま、すべて「光触媒」という一語に押し込められた。これが、現在流通している光触媒の正体である。
なぜ、ここまで無理な拡張が正当化されたのか。理由は単純である。産業と結びついたからだ。
東京大学の研究がTOTOと結びついた瞬間、光触媒は「現象の研究対象」ではなく、「商品化すべき技術」に変わった。ここで必要になったのは、正確な反応機構ではない。
売れる説明である。
電極・水溶液・外部回路という限定条件の話では、建材は売れない。
空気中で働くことにならなければ商品にならない。乾燥環境で効くことにならなければ意味がない。
だから、水中実験の反応系は、空気中でも成立することにされ、建材でも起こることにされ、誰でも分かる「分解する力」に翻訳された。
これは科学の発展ではない。産業化のための変換作業である。
TOTOと組んだから歪んだのではない。TOと組んだ瞬間から、歪まなければ商品にならなかったのである。
利害が生まれた時点で、説明は純粋な科学であることをやめる。
そこから先に残るのは、訂正できない説明、後戻りできない物語、修正されない前提だけである。
光触媒が歪んだのは、誰かが悪かったからではない。
科学が産業と結びついたとき、説明が変質するのは避けられない構造だからである。
これが、「光触媒の常識」が東京大学から始まり、東京大学の外で、商品説明として完成した理由である。
水中実験と空気中利用は、同じ反応ではない
現在、広く流通している光触媒の説明は、ほぼすべてが「水中で行われた実験」を基準に構成されている。
水溶液中。密閉または準密閉環境、」反応物が均一に存在する条件この環境で成立した反応機構を、そのまま屋外建材、室内の壁・床・天井、乾燥した空気中環境へ拡張して説明している。
これは科学的には成立しない!
水と空気は、反応媒体として本質的に異なる。
水中で成立した反応系を、空気中にそのまま適用することは、理論の拡張ではない。
説明の省略だ!
ヒドロキシラジカル中心モデルの限界
1990年代以降、光触媒の説明は急速に単純化され
「酸化チタン+紫外線+水→ ヒドロキシラジカル(・OH)発生→ 強力な分解反応」
という一つの物語に収束していった。
しかしこれは、水中実験条件に最適化された説明であり、空気中環境を前提としたものではない。
もし水がなければ反応しないのであれば、光触媒は建材や室内用途として成立しない。
現実と説明が、根本から矛盾している。
消された反応系 ― 原子状酸素の不在
1960年代までの研究では、酸素の吸着状態、原子状酸素(O⁻)、段階的な酸化反応が明確に議論されていた。
酸化チタンが本来担っていたのは、水を分解する装置ではない。空気中の酸素を活性化する触媒であった。
ところが実用化以降、この反応系はほとんど語られなくなり、水由来ラジカルだけが前面に出るようになった。
原子状酸素が否定されたのではない。語られなくなっただけである。
それは科学的決着ではなく、説明の都合による消去であった。
「ゴキブリを分解した」という物語
「酸化チタンと水と紫外線でゴキブリを分解した」
これは常識以前の話であり、科学として成立していない。
そこにあるのは、強い紫外線、水分、密閉または準密閉環境、長時間照射、熱、乾燥、酸化という複数要因の重なりであり、酸化チタン光触媒単独の能力を示す実験ではない。
酸化チタン光触媒に、大型の有機体を短時間で分解する能力はない。理論的にも、実験的にも成立しない。にもかかわらず、この話は「光触媒は何でも分解できる」という強烈なイメージを作るために使われ続けてきた。
これは科学の説明ではない。検証でもない。宣伝用に作られた物語である。
なぜこの話が必要だったのか。理由は単純である。
光触媒は本来、反応が穏やかで、変化が見えにくく、一瞬で「すごさ」を示しにくい技術だからだ。
数値も出にくい。目で見て分かる変化も遅い。
だから、誰が聞いても強烈に伝わる話が必要だった。
ゴキブリは、誰もが嫌悪感を持つ生命体として象徴的、それが分解されるという言葉は圧倒的に強いこの三条件を満たす、最も都合のよい演出素材だった。
一度この話を使えば、後には引けない。「実際はそこまでの能力はない」と言った瞬間、それまでの説明がすべて崩れるからである。
ゴキブリの話は、光触媒の能力を示した実験ではない。光触媒を“強い技術”に見せるための物語の起点だった。それだけのことである。
光触媒の定義そのものが、すでに現実とズレている
「光を照射したときに起こる反応において、光を吸収する物質が反応の前後で消費・変質せずに反応に関与する場合、その反応を光触媒反応と呼ぶ」
この定義を、厳密に満たす材料は存在しない。
反応に関与する以上、物質は必ず状態変化を起こす。それが化学の基本である。
実際の酸化チタン光触媒でも、表面の酸素欠陥は変動する、Ti³⁺ / Ti⁴⁺ 比は揺らぐ、吸着と脱離は繰り返される、表面は徐々に被覆・汚染・劣化する
つまり、「反応前後で変質しない」という表現は、現象の説明ではない。
それは、「触媒は消費されないことにして話を進める」という、学術上の便宜的な前提である。
定義が先にあり、実体は後から合わせられた。
誤解が生んだ技術の歪み
「強く分解する技術」という誤解は、ドーピングの多用、吸着材の追加、短時間試験への過度な依存
を招いた。
しかし、ドーピングは一時的、吸着は必ず飽和する、表面は被覆され機能は低下するという構造的限界を持っている。
これは進化ではない。性質を無視した補強策である。
本来の光触媒の価値
酸化チタン光触媒の本質は、大きなものを壊すこと、強い数値を出すことではない。
空気中の酸素を静かに活性化し、低濃度、長時間、表面環境を安定させる。
それが本来の姿である。
結論
光触媒に「常識」があるのではない。
あるのは、水中実験を基準とした研究史、空気中用途を前提とした工業化、強い言葉を必要とした販売現場。これらが整理されないまま積み重なった結果である。
問うべきは、光触媒ではない。光触媒に常識があると信じさせてきた説明構造そのものである。
この構造を理解したとき、REDOXが「強さ」や「即効性」を追わず、表面環境そのものを安定させる設計を選んだ理由は、自然に見えてくる。