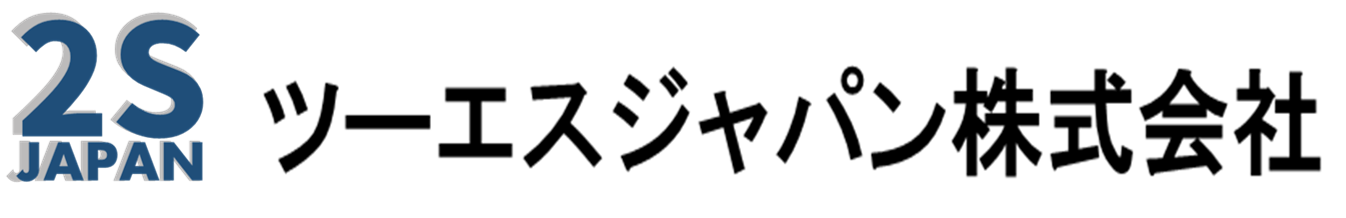― 実験と実用の境界線を引き直す ―
光触媒という言葉は、いつの間にか「条件が揃えば反応する材料」から「何でも分解する万能技術」のように扱われるようになりました。
しかし、そこには一つの大きな混同があります。実験条件で成立した反応と、実環境で再現できる効果は、同じものではありません。
この二つを同じ言葉で語った瞬間から、科学は説明ではなく“期待の演出”に変わります。
本ページは、光触媒を否定するものではありません。
ただし、「成立している話」と「広げすぎた話」をきちんと分け直すための整理です。
以下、東京大学の「光触媒の新世界 市場との対話が生んだブレークスルー」という記事から、文章や図を引用しています。
本ページの目的は、これらを否定することではありません。
ただし、「どこまでが科学で、どこからが物語なのか」を整理するためにあります。
■ 酸化チタンの作用=水中で反応する?
東京大学の「光触媒の新世界」には、酸化チタンが水や空気中で活性酸素を生じ、アルコールや植物、さらにはゴキブリまでを酸化・分解すると説明されています。
しかし、この説明は“反応構造の説明”としては成立していても、“材料としての酸化チタン単独の挙動”を正確に示しているとは言えません。
光触媒の新世界市場との対話が生んだブレークスルーより
(https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/features/f_00057.html)
「酸化チタンの作用は、まず酸化チタンに光が当たって電子が励起(エネルギーの高い状態)され、この電子が他の分子に結合してこれを還元、電子が励起された跡の正電荷を持った「穴」(正孔)が分子から電子を奪って酸化する過程です。空気中や水中でこの反応を行うと、酸素が電子と、水分子が正孔と反応するといずれも活性酸素を生じ、これはアルコールや植物の葉さらにゴキブリまでも酸化し、二酸化炭素にまでも分解する作用を持ちます(図1)。
そこでこの反応性を利用して、汚染水や大気の浄化を行おうという研究が1980年代の中頃から熱心に行われましたが、大量の水や大気を処理することはできず、研究は行き詰まりました。

酸化チタンは、水と化学反応を起こす物質ではありません。
酸化チタン単独では、水の光分解も、水の光酸化も起こりません。
図に描かれているような「水が反応して水酸基が生じ、そこから連続的に反応が進む」という理解は、実際の材料挙動とは一致していません。
ここで起きている混同は、「半導体電極系で成立する光電気化学反応」と「粉体や被膜として使われる酸化チタンの光触媒反応」を同じ構造で語ってしまっている点にあります。
■ 本多・藤嶋効果と光触媒反応は別物
北海道大学・佐藤信理氏の解説にある通り、本多・藤嶋効果は光触媒反応ではなく、光電気化学反応です。
半導体電極、対極、電解液、外部回路という“電池構造”が成立してはじめて起こる反応であり、酸化チタン単独では成立しません。
それにもかかわらず、「酸化チタン単独でも水が分解される」「水と反応して活性酸素が生じる」
といった表現が流通しているのは、反応系の前提条件が意図的に省略されている状態と言えます。
サトシンの光触媒のページ(https://satoshin.web.fc2.com/photocat/index.html)の、
「光触媒入門—12.半導体光電極反応と本多・藤嶋効果」には、次のように書かれています。
酸化チタン単独でも本多・藤嶋効果があると書いてある本がありますが、間違っています。半導体光電極セルで対極の白金がなければ本多・藤嶋効果が起こらないように、金属のついていない酸化チタンでは水の光分解あるいは水の光酸化は起こりません。~酸化チタン単独の光触媒作用の仕組みは、実用化こそされませんでしたが、本多・藤嶋効果発見の前からわかっていたことです。
■ 「ゴキブリを分解する」という表現について
酸化チタン光触媒によって「ゴキブリまで分解できる」という表現は、科学的説明というよりも、印象操作に近い言い回しです。
もし本当にゴキブリを分解できるほどの反応性があるなら、それは人の皮膚に直接触れる化粧品や日焼け止めに安全に配合できる物質ではなくなります。
この表現が示しているのは、「強そうに聞こえる」というイメージであって、実用材料としての現実的な反応量や持続性ではありません。
実際に酸化チタン光触媒が生成する活性種は微量であり、カビの胞子の表面を部分的に傷つけることはあっても、繁殖した菌層や大量の有機物を分解するような能力はありません。
■ 酸化チタン光触媒は「超親水性」なのか?
東京大学の記事では、酸化チタン光触媒の転機は「超親水性」にあると説明されています。
しかし、酸化チタンそのものは疎水性材料です。水と反応する性質も、水酸基を自発的に生成する性質も持っていません。
「酸化チタンの酸素が抜け、水酸基ができる」という説明は、反応機構としては非常に不安定で、
材料科学的に見ると成立しているとは言い難いものです。
酸化チタン単独の被膜は、親水でもなく、撥水でもなく、疎水性という挙動を示します。
水滴は玉状になりやすく、流れやすく、乾きやすく、結果として汚れが定着しにくくなります。
一方で、親水性コーティングは、水が薄く広がり、濡れた状態が長く続き、汚れを面に保持し続ける構造になります。
「親水=防汚」という図式は、現実の汚れ環境では必ずしも成立しません。
東大の黄ばんだトイレの便器を眺めていた時、酸化チタン光触媒がゴキブリを分解できるなら、黄ばみの原因菌も分解できるのではないかとひらめいた
~早速、つてをたどってTOTO株式会社(当時:東陶機器株式会社)との共同研究が開始されました。〜
この共同研究の中で見つかったのが「超親水性」という現象でした。酸化チタン光触媒をコーティングした表面は、極めて水になじみやすくなり、水をかけても薄い膜となって流れてゆきます(図2)。これは学術的に新規な現象であり、1997年やはりNature誌に掲載されました。
これは、光触媒の効果によって油汚れが分解されること、また酸化チタンの酸素が光照射によって抜け落ち、これが水分子と反応して水酸基を作ることにより、表面と水分のなじみがよくなることによります。これによって汚れは洗い流され、長時間自己浄化効果が持続します(図3)。
■ 「新しい光触媒」はなぜ姿を消したのか
東京大学の記事では、鉄や銅を付着させた「新しい光触媒」が可視光で高効率に反応し、2014年には製品化される予定とされています。
しかし、現在に至るまで、この技術は市場に定着していません。理由は単純です。
ドーピング金属は触媒ではなく、酸化されれば機能を失います。
反応は一時的で、継続できません。
さらに、金属はやがて反応点を塞ぎ、酸化チタンの機能を阻害し、材料そのものを劣化させます
いわゆる「触媒毒」として振る舞います。
反応効率のグラフは描けても、寿命のグラフは描けない。
これが実用化できない最大の理由です。
これまでの酸化チタン光触媒の難点は、太陽光線のうち紫外線のエネルギーしか使えないため、屋外など強い紫外線の当たる場所でしか、その性能が発揮できないという点です。可視光線のエネルギーが利用できれば、酸化チタン光触媒の応用にとって革命となります。〜
その解決策は、酸化チタンの表面に、鉄あるいは銅イオンから成る「助触媒」を付着させる方法でした。こうすると、酸化チタンから助触媒へ電子が直接励起される「光誘起界面電子移動」が起き、エネルギーの低い可視光でも十分利用が可能になります。また、この助触媒は2つの電子を受け取って酸素を還元でき、この段階の反応効率をも大いに高めます。この2つの効果の合わせ技により、従来の10倍以上の反応効率を実現したのです(図5)。〜
「新しい光触媒は、紫外線を含まない蛍光灯の光を照射するだけで、感染性ウイルスを大幅に不活化させます。すでに空港や病院などで検証試験が行われ、優れた抗菌・脱臭作用が確認されています。2014年中にこの新しい光触媒を利用したフィルムやペンキ、ガラスなどが製品化され市場に出る予定です」。
今後この新しい光触媒は、室内の揮発性有機化合物やアレルゲンの除去、壁紙や床材、空気清浄機などへの応用が期待されています。「市場との対話」から生まれた新たな光触媒は、今後も産学連携の良きモデルとなりそうです。

■ 誇大表現が生まれる構造
問題は、酸化チタンが光触媒であることではありません。
問題は、反応条件を省略し、反応量を無視し、持続性を語らず、実環境での再現性を検証せず、
それでも「分解」「浄化」「自己洗浄」という言葉を使ってしまうことにあります。
それは科学ではなく、「物語の構築」です。
■ まとめ
酸化チタンは光触媒です。
しかし、
水と反応するわけではなく、ゴキブリを分解できるわけでもなく、超親水性が自動的に防汚を生むわけでもなく、可視光化すれば万能になるわけでもありません。
成立している反応と、広げすぎた解釈を一度切り分ける必要があります。
このページは、光触媒を否定するためのものではなく、「語りすぎた部分を静かに戻すため」の整理です。